「ソフトバンク」は「近鉄」だった?
- 2021.04.21
- プロ野球史 野球史
- オリックス, グレートリング, ホークス, 京セラドーム大阪, 別所昭, 千葉茂, 南海, 南海ホークス, 南海軍, 南海鉄道, 南海電気鉄道, 大阪ドーム, 大阪近鉄バファローズ, 太平パシフィック, 小林一三, 山本一人, 巨人, 戦時体制, 日本プロ野球歴史秘話, 日本職業野球連盟, 日本野球連盟, 東西対抗戦, 没収試合, 球界再編問題, 産業戦士, 神宮球場, 神田武夫, 福岡ソフトバンクホークス, 近畿, 近畿グレートリング, 近畿日本軍, 近畿日本鉄道, 近鉄, 近鉄バファロー, 近鉄バファローズ, 近鉄パールス, 野球報国会, 関西急行鉄道, 阪急, 阪神, 陸上交通事業調整法, 鶴岡一人

日本プロ野球歴史秘話(7)
2020年、圧倒的な強さで日本シリーズを制した「福岡ソフトバンクホークス」。
いやぁ、強かったですね。
そんなホークスが「近鉄(近畿日本)」の名前を名乗っていた時期があるんです。
「近鉄って、別のチームじゃなかったけ?」
「今のオリックスバファローズだよね?」
そんな「?」が浮かんだ方もいらっしゃるでしょう。
プロ野球の歴史では、しばしばそんなウソみたいな事が起きます。
今回は、そんなお話です。
若いファンの方は、「ホークス=福岡のチーム」というイメージでしょう。
1989年のに「福岡ダイエーホークス」がフランチャイズとしてからですから、今年(2021年)でもう33年目になるんですね。
福岡に移転する前は、大阪を本拠地とする「南海ホークス」であったことをご存知の方も多いと思います。
親会社は関西地区を走る「南海電鉄」です。
同じ関西には、私鉄で路線長日本一(JRを除く)の「近畿日本鉄道」があります。
戦中・戦後の一時期、「南海」は「近畿日本」の名前でシーズンを戦いました。
つまり、ライバル会社の名前を付けていた事になります。
なぜ、そんなことになったのか?
その謎を解くには、まず「ホークス」の誕生からお話していきます。
「南海軍」誕生
「福岡ソフトバンクホークス」の祖先である「南海軍」がプロ野球に参加したのは、1938年(昭13)年のシーズンからです。
先にプロ野球に参加していた、同じ関西の「阪神」と「阪急」から球団設立をすすめられ、プロ野球の宣伝効果も考慮して設立が決定されました。
「日本野球職業連盟(1939年から日本野球連盟)」のリーグ戦が始まって3年目の事です。
1938年3月、「南海軍」の参加申請を連盟に申し入れました。
しかし、この可否を検討する連盟の総会は、少々混乱したそうです。
当時のプロ野球は、8球団によって運営されていて、「南海軍」は9つ目のチームになります。
チーム数が奇数になると、日程上どうしても1チームが余ってしまう事が、反対意見として一部の球団から出されました。
これに対し「阪神」「阪急」が、加盟が認められない場合は、リーグから脱退し関西の私鉄のよる新リーグ*を設立するという強引な態度に出たと伝えられています。
又、結成当時の「南海軍」は監督を含めわずか14名という陣容で、戦力不足も反対理由とされました。
紛糾の後、連盟は「戦力不足を補う(練習や補強)猶予期間として、リーグ参加は秋のリーグ戦からとする」という条件付きで「南海軍」の加盟を認めました。
関西鉄道会社の「絆」の勝利といったところでしょうか。
とにもかくにも、新チーム「南海軍」は船出しました。
*関西私鉄リーグ
「阪急」「阪神」が総会で持ち出した関西私鉄の新リーグ構想には、次のようなベースがありました。
阪急電鉄の創始者「小林一三(こばやし いちぞう)」は、「日本職業野球連盟」が設立される以前の大正末期、「阪急」「阪神」「京阪」など、関西の私鉄各社によるプロ野球リーグを構想しました。
沿線の球場での野球興行の収入や、観客の輸送による収益増を見込んでの事といわれています。
将来は関東にも私鉄リーグを作り、日本一を争うという壮大なプランでしたが、当時は大学野球全盛の時代で、時期尚早とされこの構想は見送られました。
実現してたらどんな野球事情になっていたのでしょうか。
想像すると楽しいですね。
戦時体制 「南海軍」から「近畿日本軍」へ
プロ野球に参加した当初の「南海軍」は、正直あまり強いチームとは言えませんでした。
球団は苦戦しながらも、入団初年度にホームラン王になり、後の名監督となる「鶴岡一人(つるおか かずんど)」や、プロ野球ニュースでお馴染みだった「別所 昭(べっしょ あきら:のちの毅彦)」、病を押して投げ続けた「神田武夫(かんだ たけお)」など、学生野球のスター選手を積極的に獲得しチームの整備を図っていきました。
しかしながら、この時期は日中戦争から太平洋戦争にいたる、いわゆる「戦時体制」のさなかで、選手の兵役が相次ぎ、思うように戦力の補強ができない状態でした。
プラスマイナスゼロのループに入っていたといえるかも知れません。
球界全体が同様な時代でしたから、既存の球団との差は縮まらないままでのリーグ戦だったというわけです。
これに加え「戦時体制」は、球団の親会社「南海鉄道(当時)」をも巻き込んでいきます。
1938年(昭13)鉄道やバスなどの整理統合を目的とした「陸上交通事業調整法」という法律が制定され、大手私鉄の統合や、中小私鉄の国有化や吸収合併が相次ぎました。
この法律の趣旨を簡単にいうと「乱立する公共交通機関を大きな会社にまとめて、路線や資源を一括で管理し効率的に運営して戦争に役立てる」という感じになりますか。
関西では「阪神急行電鉄(阪急)」と「京阪電気鉄道」が合併し「京阪神急行電鉄」となったり、関東の「東横電鉄」が「京王電気軌道」「京浜電気鉄道」「小田急電鉄」を統合し「東京急行電鉄」となる中、「南海鉄道」も例外ではなく、戦局の激しくなった1944年(昭19)6月、同じ関西をベースとする「関西急行鉄道」と新設合併を行い「近畿日本鉄道」が誕生します。
これに伴いプロ野球「南海軍」も名称を「近畿日本軍」と変更しました。
この時から「南海(のちのソフトバンク)」が「近鉄」を名乗ることになったわけですね。
野球報国会
「南海軍」が「近畿日本軍」となった1944年のシーズンのプロ野球は、とても厳しいものとなりました。
選手たちの多くは兵役にとられ、チームの編成にも影響が出る状態であったり、都市部の空襲も激しくなり試合中止が相次いだり、野球にとってまさに「冬の時代」でした。
[不要不急の娯楽]の汚名を逃れるため、「日本野球連盟」はその名を「野球報国会」とし、残った選手達を工場に「産業戦士」として派遣するなど「プロ野球の火」を消すまいと必死の努力を続けました。
しかし戦局は激しさを増し、秋季リーグは中止され、そのままプロ野球は活動を休止します。
以上の様な理由で、この年は夏季リーグのみの開催となりました。
戦前の「近畿日本軍」が戦った公式戦は、わずか35試合のみとなっています。(11勝23敗1分 6位)
「近畿グレートリング」
戦後のプロ野球は終戦の年 1945年(昭20)11月23日、東京・神宮球場の「東西対抗戦」から始まりました。
焼け跡の東京に、それぞれの終戦を迎えた選手たちが日本各地から集まって来ました。
ファン達もそれを歓迎し、終戦直後の時期であるにも関わらず約6,000人がスタンドを埋めました。
この試合は、戦後のプロ野球ブームのけん引役「青バットの大下」こと「大下 弘(おおした ひろし)」のデビュー戦でもあります。
「東西対抗戦」の成功を見て、野球関係者はプロ野球の再建に乗り出します。
復活した「日本野球連盟」は、進駐軍との交渉や球場の確保、野球用具の調達、移動の手配、選手への連絡など多岐にわたる大きな困難を乗り越え、翌年1946年(昭21)のシーズン開始へとこぎつけました。
「近畿日本軍」は球団名を「近畿グレートリング」とし、再スタートを切ります。
ニックネームの由来は「鉄道の車輪」と「融合の輪・平和」をイメージしたといわれています。
選手兼任の「山本一人(旧姓 鶴岡)」監督を中心に、戦地からの帰還した選手や新人を加え「近畿グレートリング」は戦後初のシーズンを戦います。
追記
新しい時代に向けてのチーム名変更でしたが、少々困った事態も起きていました。
英語のスラングで「グレートリング」は、下品な意味を持つことを知らなかったのです。
観戦に来た占領軍の兵士には、好評だったそうですが…
又「近畿」の発音に似た、あまり好ましくない英語もあるそうです。
ですので、英語がネイティブな方と日本プロ野球の歴史を語る時は、細心の注意が必要(?)です。
(そんなことはまず無いでしょうけど)
初優勝
「グレートリング」は、1946年(昭21)のペナントレースで球団創設以来、初の優勝を遂げました。
シーズン序盤は5割戦後の勝率でしたが徐々に勝ち星を重ね、最終戦まで「巨人」と激しく首位を争い栄冠を手にしました。
最終成績は「近畿」・・65勝38敗2分、「巨人」・・64勝39敗2分とわずか「1勝」の差でした。
実はこの勝利は、薄氷を踏んでのものだったんです。
このシーズン中に「太平パシフィック(戦前の朝日軍)」が、帰属問題で登録が認められていない選手を強硬出場させた試合がありました。
これを重く見た連盟は、該当選手が出場した4試合を「没収試合」とし、全て0-9で「太平」の敗戦との裁定を出します。
その中には「近畿」が負けた試合も含まれていて、この「1勝」が大きく効いての勝利ということになります。
《たかが「1勝」、されど「1勝」》
こんな言葉が染みるシーズンだったと言えるでしょう。
「南海ホークス」
戦時中に合併によって誕生した「近畿日本鉄道」でしたが、「元・南海鉄道」「元・関西急行鉄道」は、共に経営や社員の配置などは合併前と変わらない体制でした。
つまり「同じ名前の会社が2つある」といってもいい状態だったんですね。
戦争が終わると「南海」側から分離運動が起こされました。
元々「戦時体制」中での望まない合併でしたから、当然の流れだと思われます。
1947年(昭22)6月1日、「元・南海」は旧系列の「高野山電気鉄道」が改称した「南海電気鉄道」と合併し、元の形に戻る事となりました。
「元・関西急行鉄道」は、そのまま「近畿日本鉄道」として再出発します。
それと同時に「近畿グレートリング」は経営を「南海」側に移し、「南海ホークス」に名称を変更しました。
「ホークス」の名前は「南海」社内の公募で決められたそうです。
「ホークス」のニックネームはここから始まり、現在まで長きに渡りプロ野球ファンに愛され続けています。
エピローグ:「近鉄」とプロ野球
「南海」分離によって、一旦プロ野球から退いた「近鉄」でしたが、1950年(昭25)に再びチームを興し、創設間もない「パシフィックリーグ」に参加します。
沿線の名産である真珠をニックネームにした「近鉄パールス」は、大学野球出身者で固められたスマートなチームでしたが、成績の方はあまりパっとしませんでした。
本拠地は沿線の「藤井寺球場」です。
1959年(昭34)、元「読売ジャイアンツ」の「猛牛:千葉 茂(ちばしげる)」を監督に迎え、チーム名を「近鉄バファロー(1962年からはバファローズ)」に変更しました。
以後、「猛牛打線」「いてまえ打線」に代表される、豪快さが売りのチームとしてファンに愛されました。
メジャーで活躍した「野茂英雄(のも ひでお)」が在籍したチームとして覚えている方もいらっしゃるでしょう。
1997年(平9)大阪市内に完成した「大阪ドーム(現 京セラドーム大阪)」を新本拠地とし、「大阪近鉄バファローズ」となります。
2004年(平16)経営の見直しからプロ野球からの撤退を決定し「オリックスブルーウェーブ」との合併を発表、これが日本中を巻き込んだ「球界再編問題」のきっかけとなりました。
この年を限りに「近鉄球団」は消滅し、わずかな名残りが合併相手の「オリックス」のニックネーム「バファローズ」として残っているだけです。
「ホークス」が遠い過去に「近鉄(近畿日本)」を名乗っていた経緯、おわかりいただけたでしょうか?
「ホークス」が「近畿日本軍」「近畿グレートリング」だった期間は3年と少しです。
このわずかな時期に、これだけの出来事が詰まっているんです。
「プロ野球の歴史」って掘れば掘るほど、新しい事と出会えて楽しいですよ!
参考文献
『プロ野球70年史 歴史編』ベースボールマガジン社 2004年
『鈴木龍二回顧録』鈴木龍二 (著) ベースボールマガジン社 1980年
『南海ホークスがあったころ 野球ファンとパ・リーグの文化史』
永井 良和・ 橋爪 紳也(著) 紀伊國屋書店 2003年
『近畿日本鉄道 公式サイト』https://www.kintetsu.co.jp/
日本プロ野球歴史秘話(7)/「ソフトバンク」は「近鉄」だった? (了)
-
前の記事
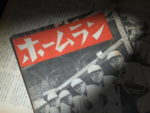
プロ野球史へのお誘い 2021.03.09
-
次の記事
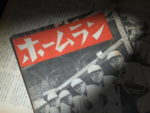
大正時代にプロ野球チームがあった?! 2021.07.05